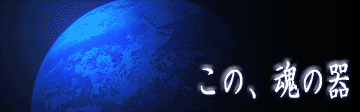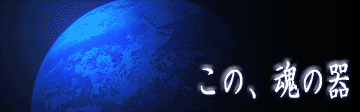「あ」
と小さく声をもらしたファイと柚己が見守る内に、静かに、滑るように、ドームのシェードが左右に分かれていった。
暗灰色の宇宙に色鮮やかな星々。
ソファに座った時に、丁度目の前に広がるのは、あれは海。
青い、青い星が、確かな存在感を持って宇宙に浮かんでいた。
太陽の残滓にきらめく、青白い櫛形の光線。
黒に無数の光を散らばめた夜を残して、輝く青い惑星の向こうに太陽が消えていく。
ひどく長く、やけに短い時間。
太陽が、沈む。
その陸地の部分一面に、人工の灯火がきらめく夜の地球が後に残された。背後の宇宙が、暗さと深みを増したようだった。
「……奇麗だね」
ため息をつくように、ファイが呟いた。
「だろ? けど、あの光みんな、そこに人間が住んでるってことなんだぜ。ちょっと、ぞっとしないか?」
「そう?」
「なんて言ってもな、住んでた時は、どこもかしこも人で溢れ返ってて、もういい加減にしてくれって感じだったけど、こうして宇宙からあの光見ると、実は、なんかほっとするんだよ。人口の増加はシャレになんないとこまできてるってのも、地球自体、もう壊れる寸前だってのもわかってんだけど、こうして見てると、ただ、なんか、きれーだなって思うんだよな。このまま……あの星が、壊れて、誰も住めない惑星になっちまうのは、ツライよな」
「あの惑星は、この宇宙の中でも、目立って色鮮やかで、賑やかな音楽を奏でてた。でも、その音楽は、時々悲鳴に聞こえたよ。崩壊の調べは、怖くて、でも、すごく奇麗だから、ぼくがぼくらだった時は、あの惑星がやがて奏でる崩壊の調べを、少し楽しみにさえしてたけど、今、ぼくは、なんだか哀しい」
その哀しみは後悔だろうか。
柚己は、そっと尋ねた。
「ぼくら、でいた方が良かったか?」
「ううん。哀しくても、ぼくがいいよ。ぼくらだったラムダが言ってたんだ。ぼくになるのもそんなに悪くないって。広がりはなくなっても、その分、ぼくが濃くなるような気がするって。その時は、それがすごく怖くて嫌だったけど、今は、ラムダの言ったこともよくわかるよ」
「どっちがいいのか、俺にはよく、わかんねェけど。どっちも経験できたってのは、きっといい事だったんだろうな」
「ツェータも、ぼくらになれたらいいのにね。ぼく、でしかわからないこともあるけど、ぼくらにしかわからないことも、やっぱりあるから」
「そうだな。一度ぐらいは、自分以外の精神と融合するってのを、試してみたい気もするな」
「リンクする?」
と、ちょっと首を傾げ、ファイが問いかける。柚己は、思わずドキリとした。リンクには俗語で、SEXという意味もある。ふと、そっちの意味に捉えそうになって、少し顔が熱くなる。
どぎまぎしながら柚己は首を振った。
「いや、それは、できねェから」
(本当に? もう一つの意味でなら、可能なのかも。これだけ精巧に出来てんなら、きっとそーゆー機能も……って、俺はなに考えてんだ!?)
「ニンゲンって、それが不便だよね。ツェータはサイボーグじゃないの?」
「えっ、いや、俺は、機械化してねェよ。一応、全部生身のまんまだから」
「生身の身体って、どんな感じ?」
「どんなって、言われても」
言い悩む柚己の顔を覗きこむようにして、ファイが言った。
「触ってみても、いい?」
ドキリ、と再び心臓が高鳴る。
「え、あ、別に、いいけど」
ぎこちなく頷いて、柚己はファイの白くて細い指先が、左の手の甲をすべるように触れるに任せた。
その指が触れた場所が、火傷したように熱い。
「ぼくより少し、あたたかいね」
「俺、平熱、高いから」
動揺のあまり、意味のない返事を返してしまう。
「ニンゲン同志なら、リンクできるのにね」
名残惜しげに手を離し、呟いたファイの言葉に、柚己はやけに大きな声で反応してしまった。
「えっ!?」
「ぼくが、リンクしてぼくらになって、遠くまで広がる時、ぼくらは、いろんな場所で、幾つものリンクの輪を見つけたよ。それはとても小さいけど、すごくあたたかかった。ニンゲン同志のリンクの光も、いっぱいあったよ。ぼくが、ロボットじゃなかったら、ツェータともリンクできるんだよね?」
「……」
(それは、そーゆーことか? 人間同志のリンクってのは、やっぱそーゆーことなのか?)
顔ばかりか、頭の芯まで熱い。痺れるような熱に、眩暈がする。
「ツェータ? ぼく、ツェータにありがとうって言い忘れてた」
「え、なにが」
ふいな言葉に、柚己は目をしばたたいた。身体の奥の行き場のない疼きが、思考力を鈍らせていく。
「あの時、ぼくに……魂があることを否定しないでくれて、ありがとう。ぼくは、よくわからないけど、それがすごく嬉しかった」
「あれは……俺にも、よくわからない。お前自身は、どう思う?」
「魂がどんなものか、ぼくにはわからないよ。でも、宇宙は音楽に満ちていて、音楽は、存在の証みたいで。魂こそが、音楽を奏でるのかもしれないとも思う。もし、そうなら、ぼくにも、ぼく自身の音楽があると思う」
「それなら、やっぱりお前にも魂はあるんだと思うぜ」
「ありがとう、ツェータ」
ファイが微笑む。
その微笑みに、柚己はいつの間にか、記憶の糸を握りしめていたことに気付いた。
「俺、今、急に思いだしたよ。お前みたいなのをなんて呼ぶか」
「なんて、呼ぶの?」
「ずっと前に、なんかのブックフィルムで見たんだ。ロボットは、プログラムによって特定の入力と出力を行うシステムだけど、人間そっくりの、いや、機械で出来た人間のことは、アンドロイドって言うんだよ」
|