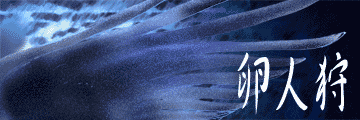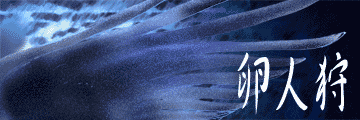「シェラ?」
シェラは漆黒のマントを脱ぎ捨てると、拳を握りしめ、唇を噛み、目を閉じた。
「シェーラ?」
「……う……くっ」
喉の奥から押し殺した苦鳴がもれ、シェラの身体が小刻みにふるえる。
ほんのりと上気した肌と熟した果実のようなその肢体が、彼女の怒りの陽炎をまとってふるえる様は、ひどく艶かしくて、こんな時だというのに、ルーダはその身を抱きしめて、はち切れそうな胸のふくらみに歯をたてて、噛み千切り、全部食べてしまいたいような衝動に駆られた。
発作的なその衝動を、目を塞いで振り払い、再び目を開けたルーダは、ようやく、彼女がなにをしようとしているのかに気づき、咄嗟にその手を取った。
「おい、よせよ、シェラ。お前地上生まれだろ、だしたこともない羽根なんか」
ルーダが、指先から伝わる、痺れるような官能の感触に浸る間もなく、
「離して!」
叫ぶように吐き捨て、シェラはルーダの手をふりほどいた。
そして、その激情に任せて、背中に最後の力を込める。
メリッ
「あ、ぐっ」
肉の裂ける嫌な音をたて、シェラの白い背中がわずかに盛りあがり、シェラは悲鳴をあげた。
「う、あっ」
「シェラ!」
「あ、あ、う……ああ、あ、ぐ、あぁっ!」
その両目から涙をふりしぼり、シェラが高く、天へとつき抜けるような悲鳴をあげた瞬間、
ズルッ…びしゃっ……
ピンク色の亀裂が白い背中に走り、肉を裂いて、黒く濡れた翼が滑り落ちた。薄紅の血がボタボタと滴る。
「う、あ……」
じっとりと汗ばんだ額を片手で拭い、シェラは自分の背中を苦痛に満ちたまなざしで振り返った。
背中の羽根は、とめどもなく流れる血に染まり、力なく垂れさがっている。ドロリとしたタール状の翼は、ひきずりだされた内臓のように、それ自身なんの力もなく、ただ痛みだけを伴って、そこにあった。その翼を拡げることも、ましてや空を駆けることなど、できそうもなかった。
薄紅色の彼女の血は、止まる気配もない。
流れ続ける血に、シェラは立っていられずに、その場にへたり込んだ。こんなとこで地面に座りこむなんて、と屈辱的な想いも、その痛みと喪失感には勝てそうになかった。
「シェラ、おい、大丈夫かよ」
「……」
唇を噛みしめて、シェラはふるえている。両手を交差させてその身を抱き、ぎゅっと眉根を寄せるシェラに、ルーダはちょっと考え込むように首を傾げ、
「……シェラ。シェラシン、きれいだな」
感嘆の吐息をもらし、子供のように笑った。
もう、自らの内から突き上げてくる衝動を、抑えこむのはやめよう。そう決めたら、ルーダは、ひどく純粋な悦びが己れの身体を満たすのがわかった。
「? うっ、うあぁっ!」
不審げにルーダを振り返りかけ、シェラは、身体をわずかに動かした途端に走る激痛に、悲鳴をあげた。
もう、なにも聞こえない。無邪気な口調で続けるルーダの言葉は、耳に届かなかった。シェラはただ、生まれてこのかた、一度も経験したことのない痛みに、閉じた瞼の奥から涙をふりしぼり、苦痛に呻いた。
「シェーラ、高慢で尊大でプライドの高いお前が、そんなふうに地面に這いつくばって泣き喚く姿を、俺はずっと夢見ていたよ。それっきりにしてしまうのが惜しくて、たやすく手に入れるのが勿体なくて、ずっとためらってたけど、俺はずっと夢見てたんだ。……きれいだな。傲慢な気高さをかなぐり捨てて、恥も外聞もなく泣き叫ぶ姿。いいな、ゾクゾクするよ」
淡いピンクにまみれ、背中を抱きしめるシェラは、ルーダの声などまるで聞こえず、ただ言葉にならない悲鳴をあげ続けている。
はるか、彼方の空を仰ぐように、ふるえて我が身を抱くシェラに、ルーダが獲物へ忍び寄る肉食獣のように歩み寄る。
「ホント、きれいだぜシェラ」
薄紅色の血にぬれて、布切れのように垂れ下がるシェラの翼を、ルーダは片手で無造作に掴んだ。
途端、感電するような痛みに、シェラが弾かれたように振り向く。
「な、に……を!?」
掠れた声を絞りだして問いかけるシェラに、ルーダは底の知れない優しげな微笑みをうかべ、
ズルリ……
「あぐっ!」
その手が、いともたやすくシェラの背中から黒い翼をひきずりだした。
わずかに蠢く黒い神経の束が、翼の根元から続いている。シェラの中から生まれた、そのビクビクと痙攣するタール状の黒い塊は、なんだかひどくおいしそうだった。口に含んで舌でころがして、その感触を確かめてみたくなるのを堪えて、地面に放りだす。あまり根は深くなかった神経の束も共に引き抜かれ、ベチャリ、とぬれた音をたてて地面に落ちた。
シェラのむきだしの白い背中には、ぽっかりとピンク色の穴が開き、そこから薄紅の液体が勢いよく迸っている。
ルーダはふと、その傷口に吸いついて、ぜんぶ飲み干したくなった。カニバリズム趣味はないと思っていたが、それがシェラなら、ぜんぶ飲み干して食べ尽くしてみたい気がした。
「う……あ……」
悲鳴をあげる力もなく、シェラは両手で自分の身体を抱えこんだまま俯せに倒れこんだ。ルーダは抑えきれない笑顔をたたえ、それを見守る。
「大丈夫。楽にしてやるよ、愛しいシェーラ」
くずおれたシェラの肩に手をかけ、ルーダは更にもう一方の翼を勢いよく引き抜く。
「っ!!」
その瞬間、最後の力をも失い、シェラは意識を手放した。
黒い。
黒い翼。
最後に脳裏をよぎるのは、夜の闇よりなお暗い、漆黒の翼。
世界をその一色に染めあげて、灰色の空へと舞いあがる。
黒い翼。
誰の背にもあったはず。
空を駆けるあの、翼。
|