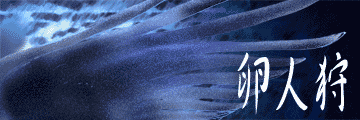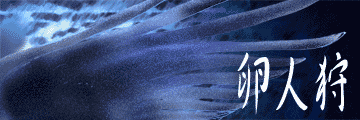〈サキは死にたいの?〉
「殺されたくないのよ! 天使に!」
〈でも、ルーァはそんなことしないよ〉
「だって、卵人を殺さない天使がいるの? 天使なら卵人を憎んでいるでしょ?」
「憎んではいない、誰も。あなたは、天使を恨んでいるのか?」
憂いを含んだルーァの呟きに、サキは泣きだしたいのを堪えて言った。彼女はもう叫んではいなかったが、その声はひどくハッキリと聞こえた。
「みんな殺されるわ、いずれね。あたしは、天使に狩られる獲物よ」
そして自らの額と左胸を指し示し、
「この赤い印をめがけて、天使達が炎の矢を放つのよ。それで平気でいられる? あたしは……恨んでる、憎んでる、恐れてる。でも……あなたは本当に天使なの?」
ふと、声を潜めて問う。
ルーァは、彼もまた、自分にそれを確認させるかのように、ゆっくりと言葉を刻んだ。
「天使だよ、私は」
「あたし、あなたが天使なんて信じられない。でも、もしもあなたが、ルーァが天使なら…… あたし、全部の天使を恨まなくてもいいのかもしれない。ほとんどの天使を憎んでるけど、全部の天使を恐れなくてもいいのかもしれないね」
囁くように言って、サキは少し、微笑った。
いつか。
いつか自分は彼等のために、命を失うかもしれない、ルーァはふとそう思い、
(それでもいい)
なんのためらいもなく、心の内で呟いた。
見た事もない翠緑の、きらめく瞳の少女が、自分のために、心底憎む種族にほんの少しでも赦しと猶予を与えてくれるなら。その瞳をいつまでも見つめていられるなら。ましてや、憎むべき種族の自分に、微笑みさえ向けてくれるのなら。
金色の少年の幻影をまとい、身体の内に染みこんでくるような声で笑う、少年の声が聞こえるのなら。痛いほどの安らぎを宿した淡く光る卵が、いつまでのこの肩にあるのなら。
(それでもいい)
ルーァは祈りにも似た想いで呟いた。
と、その物思いを切り裂くように、
フシュッ
サキの左の胸に、ゆらめく赤い花が咲いた。
真紅の花は鮮やかな花びらを散らし、サキの胸に、ふいに生まれいでたかのように。
「え?」
急に弾けた鮮明な色に、サキは視線を落とし、自分の胸に咲く真紅の花を、不思議そうに見つめた。
胸が熱い。挫いてしまった足首なんかよりももっと、灼つくように胸が熱い。
「あ……熱、い……熱い、熱い!」
口にだした途端、その熱に耐えきれず、サキは悲鳴をあげて、両手で赤い花を引き千切ろうとした。その両手が赤く染まる。
それは炎。サキの胸に咲くのは炎の花。
肉の焦げる臭いが周囲に漂い始める。サキは焼けた両手を押さえ、苦痛に歯を食いしばった。その姿に、弾かれたように多良太の悲鳴があがった。
〈サキ!? ルーァ、ルーァ、サキが! いやだ、サキを助けて、ルーァ! ルーァ、熱いよ!〉
多良太の叫びはガラスの破片となって、呆然と我を失っていたルーァを呼び戻した。
「サキ!」
まろび崩れるようにサキへと手を伸ばし、ルーァが右手をサキの胸の花を背中へと押しだすように突きだすと、炎を吹きあげていた真紅の花は、細長い矢となり、やがてジワジワと小さくなって、消えた。
だが、サキの胸に咲いた花は、今度は彼女自身の血の色によって、更に大きく大輪の花を咲かせようとしている。
〈熱いよ、熱いよ、ルーァ! 熱いよ!〉
「……あっ…う……ぐ………っ」
あまりの痛みと熱に、言葉を無くしたサキに代わり、熱さを訴える多良太は、サキの言葉にならない悲鳴を聞いているのだろう。ルーァは、蹲ったサキの傍らに片膝をつき、そのあまりに細い肩を抱いた。
「サキ」
小刻みにふるえるサキを抱いて、その名を囁くルーァの耳に、耳馴れぬ二つの声が届いた。その声の主は、サキの背中の方から、あの炎の矢が放たれたとおぼしき方角から聞こえた。
|