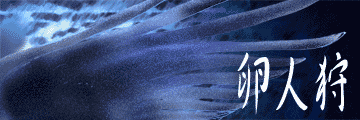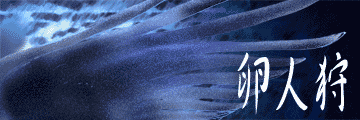看守の女天使は、沈殿する異臭を避けるように、階段を半ばまで降りた場所に立ち止まり、
「あと二日と八時間だよ」
「あと一日と十三時間だ」
ことあるごとに、狩りまでに残された時間を告げては、獲物達の恐怖を煽り、酷薄そうに笑った。そして、牢内に満たされた恐怖を感じると、満足そうにまた階段を昇って去っていく。
サキは、その女天使が訪れる度毎に、一人、恐怖ではなく怒りを募らせていた。
恐怖や畏怖や絶望ではなく、怒りを抱くコツは唯一つ。
夜毎の夢を思いだすことだ。
捕らえられた日の夜から、途切れがちの浅い眠りの中で繰り返し見る夢は。
(ノーナ叔母さん……)
狂気の炎で、弾けとんだノーナの首。
サキは夢の中で、声にならない叫びをあげて、なんとかノーナを死の定めから逃そうとするのだが、それは、決して叶うことはなかった。夢の中でノーナはいつも、サキがどれほど心と体で訴えても、あの時と同じ言葉を繰り返した。
決して止めることはできないと、これはもう決まってしまったことなのだと、過去の記憶でしかないのだと、わかっていても、わかっているから尚更、絶望に手足が冷たくなった。瞼の奥が、灼けそうに熱かった。
「サキ!? あたしを一人にするのかい? お前がいなくなったら、あたしゃこの先どうやって生きてけばいいのさ! それに、お前一人をみすみす見殺しにしたら、死んだ姉さんになんて言い訳したらいいのさ!」
「駄目だよ、サキ! お前が行けば、あたしは助かるからって、そんなバカな考えは捨てちまいな!」
ノーナの言葉を夢の中で繰り返し聞くほどに、ノーナが自分を愛してくれたことを……例えそこに自分可愛さも含まれていたとしても、そんなのは小さなことだと思えた……確信し、サキは心からとめどなく血を流した。
裂けて痛い心から流れる血で、目の前が赤く霞む。翳んだ目で見れば、天使のぞっとするほどの美しさも、心に燃える憎悪の炎を消すことはできない。
(あたしの炎を、あいつらに消すことなんてできない)
例えそれでこの身が燃え尽きても、この炎を消しはしない。
これは、復讐の炎。
「いよいよ明日の朝だよ。楽しみだね。お前らの薄汚い命も、明日の日没までには消えるだろうよ」
その日の夜半、薄く嘲笑って、看守が告げた。
淀んだ絶望の中に、ピリリと緊張が走る。
誰かが、細くすすり泣いていた。
誰かが、耐え切れずに「嫌だ! 死にたくないっ」と喚いた。
誰かが、獣のような呻き声をあげた。
誰かが、狂ったように壁を叩いていた。
サキは、小さな両手を膝の上で握りしめ、目を閉じて、自分の中の暗い色をした炎を、静かに感じていた。
この炎が胸にある限り、恐れたりしない。
たとえ、狩られて死すのが定めだとしても、天使達が望むような恐怖と絶望を抱いて、彼らを喜ばせるような真似はしない。
(最期まできっと、あいつらの顔を睨みつけてやるわ)
自分から恐怖を引きだそうと、どれほどの苦痛で嬲り者にされたとしても、
(あたしは、負けない)
|