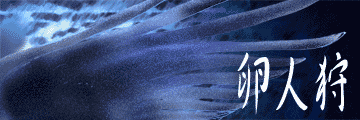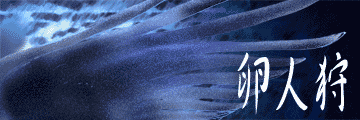ふいな問いに目をしばたたかせ、ラァザ・流黄(ルキ)は戸惑いがちに答える。
「なんだよ唐突に。俺は地上生まれだぜ、そう言ったろ?」
「あ、そうだっけ」
言って、ぼんやりと暗い夜空を見上げる横顔に、ラァザは首を傾げた。
「どうしたんだよ急に。お前は天上生まれだよな? どの位経つんだ?」
「忘れちゃったよ。けど、随分昔のような気がするなぁ」
「それで? 忘れちまうほど昔のことを、なんで急に言い出したんだよ、リィタ」
名前を呼ばれて、リィタ・鳴朱(メイシュ)はラァザを振り向き、少し笑った。
「いや、今日さ。懐かしい奴に会ってね」
「向こうの知り合いか」
リィタは、天上ではラディケルと呼ばれていた。懐かしいその呼び方。懐かしい知り合い。
リィタ=ラディケルはふと夜空の混沌に目を向け、
「うん。『白頭のサフィリエル』って、結構有名だったんだよ」
その姿を思い描くように、遠くを眺めやった。
地上の偽りの光と、天を覆う厚い雲の波が、混じりあい、蠢いていた。ドロドロに溶け合い、淀んだ穢れが天空から滴りおちてくる。
「白頭? 白毛なのか、そいつ」
「うん、生まれつきの白髪でさ。かなり露骨に蔑まれてたけど、その翼の見事なのは、みんな認めざるを得なかったよ。あれで髪が黒でさえあればね、たぶんかなりの高位天使になれたと思うよ。なんでか絶対に、染めようとしなかったけど」
「変わり者だな」
「ま、そうだね。俺の知ってる限りじゃ、一度も無性を崩したことも無かったしね」
「真性の変わり者だな。ちょっと異常じゃないのか、それ」
「だからさ、いろんな意味で忘れられない存在だったんだよね」
「そいつが地上に降りてきたのか」
「そう。それで……」
「それで?」
一瞬言い淀んだその先を促され、
「ううん、なんでもない。それはいいんだ」
ハッとしたようにリィタは首を振った。
「なにがいいんだ?」
「いいんだよ。ただ懐かしくてさ、忘れてた天上のことを、ちょっと思いだしちゃっただけ」
リィタがなにかを隠していることはわかったが、ラァザは敢えてそれを追及しようとは思わなかった。言いたくないことをムリに聞きだすのは趣味じゃない。だから、乏しい天上の知識を確認するように、ただ尋ねてみただけだった。
「ま、いいや。俺は天上のことはよく知らないけど、確かみんな羽だしてるんだろ?」
「そりゃそうだよ。翼のないのは、生まれつきの不具者か罪人だけだもの」
地上に降りて以来、その翼を忘れた自分を想いながらリィタは言った。
「じゃあ、さしずめ地上の俺達は、翼をもがれた堕天使ってとこか」
「罪人の国さ、地上はね。いいじゃない? それも」
「悪くないな」
「そうだよ、だって……」
「しッ!」
言いさしたリィタを鋭く制し、ラァザが小声で囁いた。
「狩人だ」
「え!?」
その視線の指し示す向こうには、三人の天使。揃って露出度の高い黒い服を着込み、その腰に下げているのは、黒壇の狩人の弓。
一人は小柄な少年体の天使で、ずば抜けて長身の天使に寄り添うように立ち、長身の天使はもう一人の女天使の耳元になにやら囁きかけている。
卵人を狩るだけならまだしも、暇を持て余し、欲求不満になった彼等に、無理に彼等の居城に連れ去られた天使達も多いと聞く。そこでなにがあったのか、そのまま二度と姿を見せない者もいれば、廃人同様になった者もいるようだ。少なくとも、マトモな状態で戻った者がいないことは確かだ。
だが、その後の彼等の報復が恐ろしく、自分も同じ目に合うかもしれないと、誰一人それを表だって責めたりはしなかった。むしろ、彼等に連れ去られた誰かがいれば、自ら忘れ、最初からそんな天使はいなかったかのように振る舞うのが常だ。
できることなら、関わり合いにはなりたくない。
「なんでこんな所に」
声を潜め、不審と不安の入り交じった瞳で、闇の向こうに佇む闇の狩人達を窺い見る。
「さぁな。とにかく、下手な難癖つけられたらヤバい。向こうから行こう」
それにはもちろん、リィタも賛成だった。
だが、来た道を引き返そうと身体を捻る直前、リィタは、彼等の視線がまっすぐこちらに向けられていることに気がついてしまった。それも、自分一人に注がれているように思えるのは、恐怖のための錯覚だろうか。
「……でも、こっち見てるよ。近づいてくるよ、どうしよう、ねぇ!」
こちらへと歩み寄る狩人達に、リィタは悲鳴に近い泣き声をあげた。
|