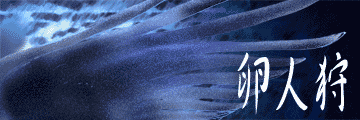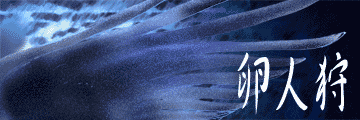「そしてあんたはあたしの傍で、あたしの獲物を横取りしてごらん。捨てた卵につまずいて、まともな狩りもできないようなあんたが、あたしの獲物を代わりに仕留めたら、あんたの卵を産んでやってもいいわ」
侮蔑を含んだシェラの挑発に、怒ったふうもなく、ルーダは笑いながら続けた。
「いいねぇ、その傲慢なセリフ。聞いてるとホント、楽しくなってくるよな。ああ、そうそう。俺が負けるのは、俺が諦めた時だぜ。俺が諦めて、参ったって言うまでは賭は続けるぜ。それでもいいか?」
「好きにすれば」
どうでもいいと、シェラは肩を竦めた。
「あんたの根気が続くまでってわけ」
「そういうこと。シェラは勝ったらなにが欲しい?」
その言葉に、シェラはちょっと表情を動かし、
「負けるはずはないから、いつかは勝つわ。勝つとわかってる勝負に、あまり高い代価を求めても酷よね。でも、あたしに対して賭を申し込んだんなら、多少のリスクは覚悟してるでしょ?」
ルーダの目を覗きこみ、試すように薄く笑った。
「なにが欲しいんだ?」
「あたしが勝ったら、あんたは女になって、あたしに殺されなさい」
サラリと口にされたその言葉に、ルーダは一瞬ぎょっと目を見開き、その後、ゆっくりと笑みを広げた。
「……怖いな。けど、いいぜ。それくらいの方が面白い」
「馬鹿ね、あんた」
シェラは、呆れたように赤い唇を歪め、賭を受けた証に、腰の弓をルーダに向かって差しだした。嬉しげにそれを受け、ルーダも同じように狩人の弓を目の前に突きだす。互いの弓を交差させるように触れ合わせ、二人の賭は成立した。
だが、それから何度か卵人狩があったが、ルーダは必ずシェラの隣にいて、その狩りを眺めてはいても、最初の賭を忘れたかのように、手出しをすることはなかった。
そしてシェラの炎の矢は、確実に、獲物に印された赤い的を貫いた。
一度か二度、シェラは獲物を指し示し、
「あたしより先に、あいつに矢を射ってみたら?」
と、ただその傍らに佇むだけのルーダを挑発したこともあったが、ルーダはいつも、
「それは駄目だよ。俺は、お前の矢を逃れることのできる獲物を待ってるんだからさ。その奇跡が見たいんだよ」
そう言って、弓に手をかけることも、その手から炎の矢を生みだすこともしない。もう、最初の賭のことは諦めたんだろう、シェラはそう思った。
(もともと、この私が狙った獲物を仕留め損なうことなどあるわけがないし、ましてや、狩人とは名ばかりのこの男に、自分の獲物を横取りできるはずもないしね)
ただ、諦めたと口にすることは自分の死を意味するから、口にだせずにいるだけなのだろう。
それならそれでもいいと、シェラは思っていた。狩りの時に自分の邪魔さえしないなら、別にどうでもいい。もともと、賭け事自体に興味は薄い方だ。
だから、今、ルーダが久し振りにその約束を口にした時、シェラは少し驚いた。だが、ルーダはまるでお構いなしに、ニコニコ笑っている。
「諦めたら俺の負けだもんな。諦めるわけないだろ。それに、お前の身体が卵で膨れるところなんか、誰も想像できないぜ。想像もできないことを想像すんのは、ゾクゾクするよな」
シェラはかすかに口元を歪め、ジロリと笑い顔のルーダを睨めあげた。
自分の身体に無数の生暖かい卵が詰め込まれるのを想像して、吐き気をおぼえる。口いっぱいにやわらかい卵をほおばって、噛み砕くその感触。グジュッ、と潰れる音が、聞こえた気がした。口の中に、白濁した卵の中身が広がり、溢れだすのを感じた気がした。
「……」
だがなにも言わず、シェラは視線を逸らし、窓の向こうの宵闇に目を遣った。
今もこの都市のどこかに白い卵が転がり、その身体の内に卵を抱える天使達が歩き回っているのだろう。その全ての卵と卵持ちの天使を引き裂いてやりたい気分だ。
「ま、とにかく。今夜は、思い切り騒いでるのが一番だよ。これから、フィム達と外に繰りだすことになってさ。皆、落ち着かないんだろ。もうすぐ卵人共を思う存分狩りたてて殺せるんだって思えばな。景気づけに、街で手頃なのをかっさらって、楽しもうぜ。お前も来いよ。って、これが俺の用事」
「……そうね。なんだか卵持ちの女を苛めてやりたい気分だわ」
「なら、俺が見つけてやるよ。卵持ちかそうじゃないか、見分けるのは得意だぜ」
「譲らないわよ」
相手は、女好きで有名なルーダだ。見つけたはいいが、それがルーダの好みだったら、譲らないと言いだすかもしれない。警戒するように睨みつけたシェラに、ルーダは軽くいなすように笑った。
「いらないって。卵持ちには興味ないからな。俺が興味あんのは、卵なんか産んだこともないような女さ。とはいえ、男だったのを女にする気は起きないしな。俺の理想はお前だよ、シェーラ」
「あたしがあんたの卵を産むまでは、ね」
棘を含んだシェラの言葉に、ルーダは我が意を得たりと頷いた。彼は、皮肉をそれと感じることがないのだろうか。
「それそれ。俺もな、それが心配なんだよ。お前は、俺が今まで感じた中でも一番強いからな」
「強い?」
シェラは、訝しげに首を傾げた。
|