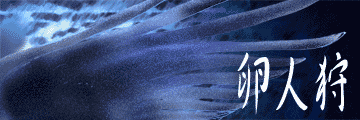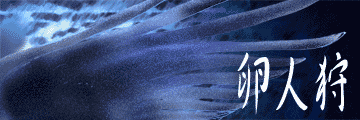重苦しい沈黙を背負ったまま、灰色の都市をどれくらい歩いた頃だっただろうか。声を発する苦しさよりも、黙っていることの方が辛くなったのか、多良太がためらいがちに、掠れた光で囁いた。
〈……ルーァ〉
「なんだ?」
ひどく優しい声音で、何事もなかったかのような平静さを装って、ルーァが多良太に視線を落とす。多良太は今にも消えそうに淡くまたたいて、泣きそうな声で問いかけた。
〈ぼくがここにいると、迷惑?〉
「なぜ?」
〈ぼくが一緒にいると、ルーァは無事じゃいられないって……あいつが言ってたよ〉
「ラディケルの言ったことは、気にしなくていい」
〈でも〉
「気にしなくていいんだ」
穏やかだが決然とした言い様にも、多良太の不安は消せなかった。ふるえる声を、抑えられなかった。
〈でも、だけど、あいつは誰かにぼくのことを言う? そしたら、誰かはぼくを殺しに、来るの? ぼくは、ルーァを危ない目に合わせるのは嫌だよ〉
「ラディケルは告げ口なんかしないさ、きっと」
多良太から、乱立する崩れかけたビル群へと視線を転じ、ルーァは静かに呟いた。無数のビルのどれか一つが崩れ落ちたら、端から砂の城のように、全て崩れていくような気がした。
〈どうしてそんなことがわかるの?〉
多良太の声に、不安以外のなにかが宿る。
「そんな気がするだけだ」
〈でも、あいつは変わってしまったんでしょう? ルーァの知ってる頃とは違うのでしょう? それでも?〉
もしかしたら、それは嫉妬、なのかもしれない。自分以外の誰かに向ける、関心や信頼に対する嫉妬、だったのかもしれない。それともただ、ルーァの抱いた想い故に、ルーァが変わってしまったラディケルをあまり快く思わなかったが故に、ラディケルに対する反感が、多良太の中に生まれてしまったのだろうか。
「姿形は変わろうと、その中身まではそんなに変わらないさ。たぶんな」
〈信じて、るんだね?〉
その声音に含まれた想いには気づかないまま、ルーァは、多良太の言葉自体の違和感に首を傾げた。
(信じる? 信じる、とはなんだろう)
聞き慣れない言葉に戸惑い、ルーァは少し考えこむような沈黙の後、呟いた。
「……よく、わからない」
信じている、なんて、そんな言葉の意味は忘れてしまった。だが、かすかな記憶の手触りは感じている。不鮮明な記憶がもどかしかった。
どうしてこの卵は、多良太という名の小さな卵は、誰もが忘れかけた言葉をこうもたやすく口にするのだろう。誰が教えたというのだろう。生まれても、いないのに。
それともそれは、生まれていないから、なのだろうか。
ルーァがそんなことを思い巡らせていた時、頼りなげな光の鱗粉をゆらし、多良太が囁くように言った。
〈ねぇ、ルーァ。ぼくは産まれてきちゃいけなかった? 生まれたらいけない?〉
ルーァには、すぐにそれに応えることができなかった。答える言葉が見つからない。
そんな問いに、答える資格があるだろうか。自分の生まれた意味さえわからないのに。
〈ぼくが生まれることは、誰も望んでないんでしょう? それどころか、ぼくに生まれて欲しくないんだ。それなら、ぼくは……〉
言葉を紡ぐにつれて、泣いているかのようにふるえる多良太の声に、ルーァは耐えかねたように口を開いた。答える資格なんてなくてもいい。多良太の涙を止められるなら。
白い卵はただ、ふるえながら光り、涙なんて零しはしないが、それでもやっぱり、確かに泣いているような気がした。
「多良太」
〈うん?〉
うっすらと涙を滲ませた、つぶらな瞳の少年が、救いを求めるように顔をあげる。揺れていたあの水槽のブルーのような鮮やかな藍色の瞳。見た事のない金色に染まる少年の髪と、背筋に沿ってさらさらと風に弄ばれているのは、髪と同じ色のたてがみか。
そんな、夢のような幻影を敢えて振り払おうとはせずに、ルーァは口を開いた。
「私には、生まれるということが、誰かの許可を得なければいけないことなのか、わからない。私自身、果たして生まれてきてもよかったのかどうか、今もまだわからない。消滅のその瞬間でさえ、わからないままかもしれない。だが、お前に生まれてほしいと思う。卵から孵ったお前が見てみたいと思う」
〈ルーァ……〉
「他の誰が望まなくても、私はそれを望む。たとえそれで、世界が終わろうと。生まれることの意味なんてわからないが、私はそれを願っている」
多良太が、多良太の幻が、ホッと微笑んだような気がした。泣きだしそうな顔のままで、微笑んだような気がした。
〈それだけでいいよ。ありがとう、ルーァ。ぼくは、それだけでいい〉
たぶん、それだけでよかった。
産まれてきたことも。生まれることも。生きることも。
誰もが否定しても、唯一人だけそれを肯してくれたなら。
たぶん、それだけでいい。
それだけで、もう怖くはなかった。
この先に待つのが、なんであったとしても。
怖くない。怖くはない、きっと。
光を帯びた白い卵を、ルーァは真っ直ぐに、瞬きもせずに見つめた。
幻に似た現実。リアルな幻を。
(それだけでいいのなら……)
始まりは幻だった。
リアルな虚構の都市。幻を現実にしたのは、自分自身。
白髪の天使は、遠のく都市の気配に、肩の上にこそ本当のリアルがあるような気がした。
今まで自分が生きてきたのは……いや、生きてはいない。生きているように錯覚してきたのは、すべて偽りの記憶。路地裏に白い卵を見つけた時、その時自分は生まれたのだと。その瞬間が、誕生の時だったのだと。
それは、そう思うことこそ、幻想に過ぎないかもしれない。
だが、それでもいい。
傍らの鮮やかなリアルがあるのなら。
それだけでいい。
それだけでいいと、微笑むように光る卵がこの肩にあるのなら。
それだけでいい。
|