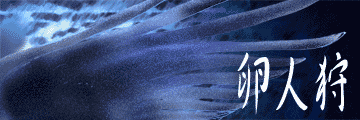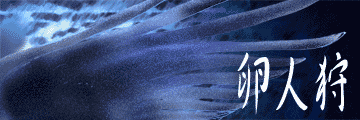肉の焼ける香ばしい香りと甘い血の匂いが漂う。高熱の炎の実が、ノーナの頭の中で弾けとんだようだ。
「!」
声もなく、その一瞬を目に焼き付けるかのように、大きく瞳を見張ったサキに、小柄な天使が笑いながら言った。その左手には、いつの間にか黒い短弓が握られていた。
「どうやって生きてきゃいいのさぁ! なんて、心配なら死んじゃえばいいんだよね。ぼくって結構、親切だよね」
サキはパッと振り返り、思わず真正面からその天使を睨みつけた。その蠱惑的な美しさも、今は目に入らない。
そんなに、大好きな叔母さんってわけじゃなかった。
噂好きで臆病でお喋りで押しつけがましくて、時々、うんざりすることもあった。だけど、悪人じゃあなかった。誰もがいつもなにかに怯えて、誰かを犠牲にして生き延びることだけを考える世の中で、彼女は善良な部類に入るだろう。
嫌いなんかじゃなかった。
それになにより、記憶もおぼろげな両親亡き後、サキのことを、唯一、打算なしにかわいがってくれた人だった。
サキの怒りに燃えた瞳を受け止めて、小柄な天使は、不快げに顔をしかめた。
「そんな目で見る権利が、お前なんかにあると思うのっ」
斬りつけるように言って、天使はフワリとローブをひるがえし、サキの肩口を蹴りつけた。ひるがえったローブの奥に、絶望のような暗い闇が垣間見えた。
「あっ」
後ろによろめき、足元がもつれる。その足首を再び天使の足が薙ぎ払う。
ドッと、尻餅をついて倒れたサキを憎々しげに見下ろし、その天使は、未だ腹立ちが治まらない様子だった。
「ムカツクこいつ。面倒だからここで殺しちゃおうか」
白い手の平を暗い空へ晒し、ノーナを殺めた力をその手に再び生みだそうとした天使を、もう一人の天使が静かに遮った。
「狩られる前の恐怖を味わうこともなく殺してやるなんて、優しすぎるんじゃないのか」
その言葉に、小柄な天使は残忍で、それだけに艶麗な笑みをうかべた。
「それもそうだね。たっぷり恐怖と絶望を味わってもらわなきゃ。いい? 狩りの時は、ぼくが必ずお前を狩るよ。お前が泣き喚いて死を乞うまで、たっぷりいたぶってやるから」
地べたに座りこみ、まるで首なしのノーナのように身動きしないサキに、少年体の天使は、愛でも囁くように約束した。
サキは動けなかった。
「必ずだよ。ぼくは、狩人だからね」
ノーナの中から、音をたててあふれだす甘い血の香が、すえた大気の中に漂っていた。
******************************************************
ガラス球の中で、彼方の空の色がゆれている。
最近、色のついた液体、大抵は有毒なものを、様々な形のガラス容器の中に入れて窓辺に飾るのが流行っていた。そのホテルの窓際にも、手の平大のガラス球が、銀の輪の中にぶら下がった形のものが一つ、置いてあった。
光に透けた色が一番美しいと聞いたが、窓から差し込む光は常に薄暗く、窓辺に飾る意味など、なさそうなものだ。地上を太陽が照らした記憶は既に遠く、古い記録の中に幾つか残っているくらいだった。少なくとも、今地上に暮らす誰も、覚えてはいなかった。この先も、二度と見ることはできないかもしれない。そんな噂は随分と前から囁かれていたが、天使達は気にしてはいなかった。
かすかな光を受けて、鈍くきらめくブルーをぼんやりと眺め、ルーァは澱んだ眠りがとけていくのを感じていた。ベッドの上で、白いシーツにくるまり、裸の肩を晒しているが、その肩に、光る卵はなかった。
卵は、ベッド脇のナイトテーブルの上に無造作に置かれたルーァの黒いコートの上で、淡く光を放っている。
〈ねぇ、ルーァ?〉
ルーァは、ブルーの液体から白い卵に視線を移し、問いかけるような瞬きを一つ。
〈ぼくね、空を飛んでみたい〉
「空を?」
〈雲の上は、明るいのでしょう?〉
「地上よりはな。暗い空の下にはいたくないのか?」
俯せの姿勢から、肘をついて身体を起こし、ルーァはわずかに首を傾げた。卵人の女ほどにしかない、薄い肩の筋肉がうかびあがる。
〈わかんない。そうなのかなぁ。でも、空の上の国にも行ってみたい。ルーァがいたとこに行ってみたいよ。地上が、嫌なんじゃないと思うけど。だって、ぼくには地上がどんなところか、まだ全然わからないもの〉
「どっちもどっちだな」
〈ルーァは上も下も嫌いなの?〉
「好きになれないだけだ」
ルーァは頬杖をついて、目を伏せた。
好きになんてなれなかった。なにもかも好きにはなれなかった。だが、焼けつくような憎悪も、吐き気のするような嫌悪もない。不快ではあったけれど、『大嫌い』だと、そう言えるほどの激しい感情はない。
好きではなかったことは、確かなのだろうが。
|