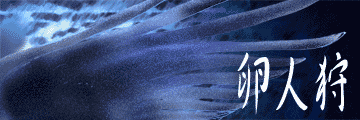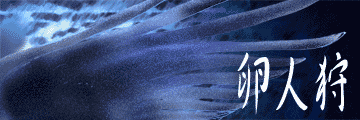あと少し経てば、一番の気晴らしが行われるが、その日が近づけば近づくほど、かえって今の焦燥感は強まってくるような気がした。
「はぁ……もう、やだ」
誰にともなく呟いたフィムは、ふと、暗い脇道に目を遣った。
二つのビルの狭間。一方のビルは、もう完全に使われてないのだろう。どんな淀んだ生命の波動も感じさせない。触れれば崩れ落ちてきそうだ。
その間を縫う暗い道に、一台のトラックが停まっていた。荷台には、からっぽの檻。暗灰色の檻は、もう随分と使いこまれているようだ。
その檻がなにに使われるのか、フィムはよく知っている。間もなく行われる卵人狩の、獲物となる卵人達を捕まえるための檻だ。
フィムは、途端に高まる鼓動と下腹部の痺れるような疼きに、少し頬を上気させ、そのトラックに歩みよっていった。
荷台の檻はまだ空っぽで、これから卵人の居住区へ中身を満たしに行くところらしい。近くには、捕獲員の赤い制服を着た男天使が二人。出発前の打ち合わせをしているらしく、二人で話しこんでいる。
フィムは、その内の一人に見覚えがあった。
少年好きのサディスト。
名前はなんていったか。確か、ロウダとかなんとか。
一度だけ、気紛れで相手になったことがあったけれど、ともすれば相手を殺しかねない、サディスティックな行為は、フィムの趣味とは合わなかった。不愉快な思いをさせられた報復に、殺してしまおうかとも思ったが、その顔立ちと背の高さは結構タイプだったから、殺すのだけはやめておいた。そしてそれきり、会ってもいない。
顔を合わせると、ちょっと面倒かも、とも思ったが、フィムはわざと気づかせるような足取りで二人に近づいていった。
フィムの知っている方の天使、ロウダが、フィムの視線を感じたように振り返り、少し眉を吊り上げた。
「フィムじゃないか。久しぶりだな」
「うん、久しぶり」
フィムはどこにでもいる知り合いに対するにみたいに、ちょっと素っ気なく挨拶した。
ロウダはわずかに首を傾げ、フィムを値踏みするような眼差しのもう一人の天使に、
「ちょっと待っててくれ」
と声をかけ、フィムの方へと歩きだした。
フィムは立ち止まり、ロウダが目の前にやってくるのを待って、背の高い相手を見上げた。
「あれから顔を見なかったが、元気だったか?」
「うん、まぁね。そっちは?」
「俺は相変わらずだ」
(相変わらず悪趣味なSEXしてるってわけ)
口にださずに呟いて、フィムは少し微笑んだ。
とろけるようなこの微笑みで、何人もの相手を骨抜きにしてきたけれど、ただ一人の相手にはまるで通用しなかった。他の誰より、その相手にこそ通じてほしかったのに。
暗い気持ちになるのを抑え、フィムは気を取り直して、囁くように言った。
「そう。よかった」
「……あまり、元気がないみたいだな」
「心配してくれるの」
「当たり前だ。俺でよければ力になるぞ」
「そう? それなら……実はちょっと、お願いがあるんだけど」
「なんだ?」
実際、下心はあるのだろうが、あまりそれが表情にでない。そういうところは、ちょっとした長所かもしれないと、フィムは思った。
「これから、獲物を見つけにいくんでしょ?」
「ああ、もうすぐ卵人狩だからな。狩人のお前は、当然参加するんだろう?」
卵人狩を行う天使たちの中でも、その残酷さ、獲物を逃がさない執念、執拗さ、獲物を射抜く裁きの炎を生みだす能力、そのすべてで他の天使達とは一線を画す集団は、卵人狩が行われない時でも狩人と呼ばれている。普段から、彼らはみな同じ、塔のように高い高層ビルで暮らし、今フィムが着ているもののように、いつも黒一色の服を身にまとっていた。そして腰や肩には、形こそそれぞれ微妙に異なっているが、色は同じ黒檀の弓を下げている。
だが、一般の天使達は大抵、暗い色の髪と瞳の色の反動か、鮮やかな色彩を好んで身にまとっていた。狩人や、先予見、捕獲者などの特別な地位にある者だけが、その正体を示す一色を身につけている。
フィムとロウダは、黒と赤と、身にまとった色こそ違うが、醸しだす雰囲気には、どこか似たところがあった。同じように、卵人を狩る、ということに深く関わっているからかもしれない。
|